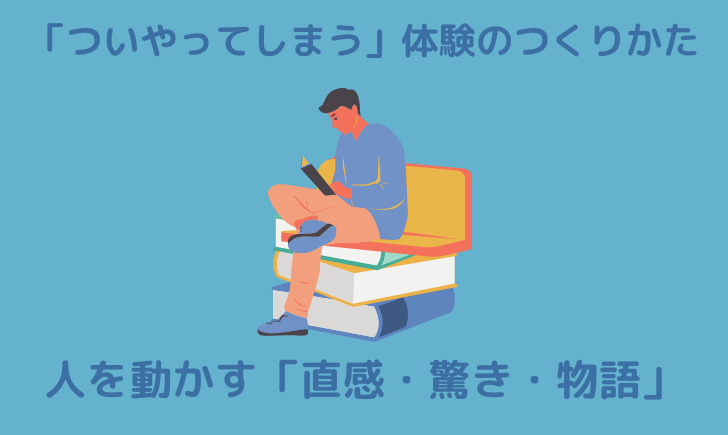今回は、2019/8/7に発行された著書『「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ』をご紹介します。
さすが体験デザインのプロフェッショナルといった印象で、著書の中にも体験デザインのノウハウが散りばめられており、最後まであっという間に読んでしまいました。
それでは、内容をご紹介していきます。
どんな悩みを持つ方におススメか?
新規事業企画、マーケティング、営業などの企業担当者の方、プライベートにおいて、コミュニケーションに悩みを持っている方に読んでいただくと参考になると思います。
私の場合は、マーケティングと新商品・サービス企画において、ユーザーの立場にたった発想を行いたいという課題から、本書を読みました。
この本を読んで得られること
①なぜ我々がゲームにはまってきたのか、その仕掛けが理解できる
②UX(User Experience)の考え方を具体的を交えて理解できる
③コミュニケーションにおける「伝え方」の発展
読もうと思った理由・期待したこと
本著を読もうと思った最も大きな理由は、現在支援している新規事業にて提供している、業務用アプリケーションのUX改善に活かせるヒントを見つけることです。
もう1点は、一緒に働いているUXデザイナーの方が、本著を紹介してくれたので、UXに関する知識を深めるには良書と思ったことです。
その為、本著から、支援している新規事業のアプリ改善案と、マーケティング施策案を抽出するヒントを考えていきたいと思います。
本の概要・あらすじ
本著では、心を動かす体験をつくる方法「体験デザイン」を、ビジネス・日常生活に応用できる3つの型について紹介されています。
- どうして子供は言うことを聞いてくれないのか
- どうして私の話は相手に伝わらないのか?
- どうしてこんなに良い商品が売れないのか?
このように、「誰かの心を動かしたい、わかってほしい、動いてもらいたい。」そういった願いに応えたいと著書が強く思いから、執筆されています。
目次(一部掲載)
第1章 人はなぜ「ついやってしまう」のか
・直感のデザイン
・どんなゲームが売れるのか
・メッセンジャーとしてのマリオ
・クリボーに出会ったプレイヤーが感じる奇妙なこと
・直感のデザインの構造
・おもしろそうと思わせるよりも大切なこと
…(以下省略)
第2章 人はなぜ「つい夢中になってしまう」のか
・驚きのデザイン
・ゲームの教科書としてのドラゴンクエスト
・なぜ「ぱふぱふ」なのか
・プレイヤーの予想を外すという体験デザイン
・きっかけは、ふたつの思い込み
・驚きのデザインの構造
…(以下省略)
第3章 人はなぜ「つい誰かに言いたくなってしまう」のか
・物語のデザイン
・物語はどんな形をしているか
・断片的に語る、波をつけて語る、未来に語る
・体験の意義
・成長のモチーフ1「ない」を集める
・時間は目に見えないし、問題は終わらない
…(以下省略)
終章 私たちを突き動かす「体験→感情→記憶」
巻末1 「体験のつくりかた」の使い方(実践編)
巻末2 体験デザインをより深く学ぶための参考資料
著者プロフィール
わかる事務所代表
任天堂株式会社にてゲーム機(主にWii)の企画担当をされており、企画~開発すべてに横断的に関わり「Wiiのエバンジェリスト(伝道師)」、「Wiiのプレゼンを最も数多くした男」と呼ばれています。
本著のポイント
心を動かす3つのデザインの型として、「直感のデザイン」「驚きのデザイン」「物語のデザイン」とされています。
本記事では、私が本著を読もうと思ったきっかけである、『新規サービスの業務用アプリケーションのUX改善に活かせるヒント』という観点で参考になった3つのポイントをご紹介します。
(※3つの型について全ては紹介しておりませんので、ご了承ください。)
ポイント1:直感のデザイン
日本企業に多い、プロダクトアウト思考の商品・サービスでは、「この商品はこんな機能があるんですよ。」「このサービスはこんなところが良いんですよ。」と良さ・正しさをガンガン伝えてきます。本書ではその考え方を“ユーザーを考えない”デザインとしています。
ユーザーは、まず目の前の商品・サービスとの関わり方が直感的にわかることを優先するそうです。ユーザーは、その商品・サービスがおもしろいのではなく、直感で関わり方がわかり、体験そのものがおもしろい・便利だと思うから利用するのです。
私が支援している業務アプリケーションは、この部分が欠けており、機能やメリットを押し出してしまっていました。また、ユーザーに分かりやすいデザインを心掛けてはいたのですが、ターゲットユーザーのITスキルレベルを少し高めに考えてしまっていたために、提供している業務アプリケーションを使いこなせない事が判明しました。
ポイント2:初頭効果
昔は、インベーダーゲームのようにデータ量がとても少なくシンプルなゲームでしたが、現代は技術発展によってデータ量が増え、ゲームに登場するアイテムもバラエティに富んでおり、ゲーム自体が複雑になりかねない状況になりました。
スーパーマリオも、キノコ・フラワー・スター・1UPキノコの4種類のアイテムが登場しますが、この4種のアイテムすべてを最初のステージに集中して登場させていたのです。
これは心理学の「初頭効果」を利用していて、しっかり学んでもらわなければならない4つのアイテムを、ユーザーの集中力が高い最序盤に登場させることで、ゲームの複雑さ・難解さを回避しているそうです。
このことを支援している業務アプリケーションに置き換えてみると、ユーザーがアプリケーションを使い始める段階で、特段機能説明などをする訳でもなく、勝手に使ってください的な印象になっており、序盤から、このアプリケーションは使い勝手が悪い・難しいとインプットされていたのだと判明しました。
ポイント3:タブーを使う
例として、ドラゴンクエストが上げられていましたが、ドラクエ1の一番最初は、王様から竜王を倒すように命じられて旅立つところから始まりますが、部屋の外にでようにも、扉に鍵がかかっていて、どれだけ歩き回ろうがゲームが進行しません。
試しにコントローラーのボタンを押すと、右上にコマンドが表示され、はなす、しらべるなどの、ゲームのルールと進め方を学習をします。この学習を繰り返して行くと、ユーザーは「疲れと飽き」を感じてしまい、ゲームを続けるのが辛くなってしまいます。
こういうった時に、ゲームを続けてもらう仕掛けとして、ユーザーの『予想をはずす』ための『タブー』の活用があります。タブーとは、日常生活の中で登場しないに違いないとユーザーが思っていることです。
ドラクエにおけるタブーは『ぱふぱふ』です。ぱふぱふ関する詳細は省きますが、こういった非日常的なタブーがゲームの中で起こることで、ユーザーの予想が外され、この現象が、ユーザーの『疲れや飽き』を癒し、ユーザーはゲームを継続してくれるようになるのです。
本著では、タブーのモチーフは10種類紹介されており、その中のモチーフを支援しているアプリケーションの中に入れ込んでいくことを検討する必要があると考えています。
法人向けの業務用アプリケーションなので、『ぱふぱふ』などの表現は難しいですが、アプリケーションを使い続けてもらう施策の一つに検討をしていきたいと思います。
まとめ
今回は、「誰かの心を動かす」ために書かれた著書『「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ』をご紹介しました。
私の書評では、目の前にある実案件を考えながら本著を読んでいきましたが、巻末1にある「体験のつくりかた」の使い方(実践編)では、日常生活に体験デザインの活かし方が書かれており、大変参考になりました。
この中では、
- 考える/企画
- 話し合う/ファシリテーション
- 伝える/プレゼンテーション
- 設計する/プロダクトデザイン
- 育てる/マネジメント
として紹介されており、営業担当者、マーケティング担当者は勿論のこと、『育てる/マネジメント』では、著者の子育てにおいて体験デザインを応用されたことが書かれており、非常に参考になると思います。
「子供がいう事聞かないー」と毎日カリカリされている方がいらっしゃいましたら、是非参考にしてみてください。
それでは今回はここまでといたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
本を一日一冊読めるようになりたい方はこちらの記事もどうぞ↓↓↓