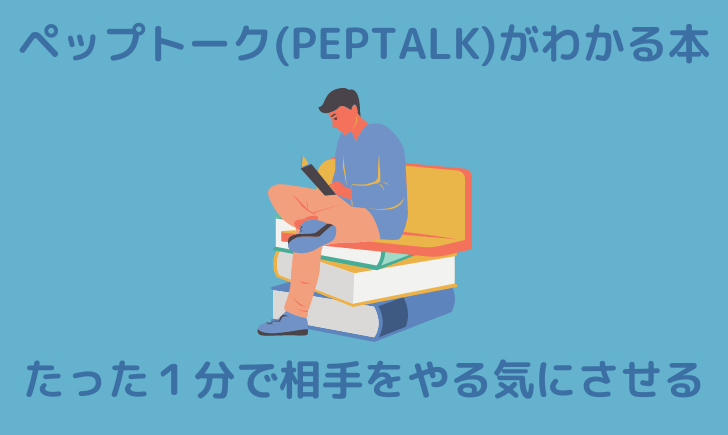今回は、2017年7月6日に発行された著書『たった1分で相手をやる気にさせる話術PEP TALK 』をご紹介します。
●書評を動画で見ることもできます(↓)
本著は、読者が直ぐにペップトークを考えられるように、テンプレートも用意されており、ペップトークを理解する上で、最も分かりやすかったのでご紹介します。
はじめに、本の紹介に入る前に、あなたは『ペップトーク』という言葉を聞いた事あるでしょうか。
ペップトークとは、『励ます技術』のことで、元々は、スポーツの試合前に、監督やコーチなどの指導者が選手に向かって行う激励のショートスピーチの事を言います。
あなたにペップトークをイメージしていただくために、有名な実際のペップトーク例をご紹介します。(動画:50秒)
熱いですよねー!
これは、立命館大学を率いる古橋監督のペップトークです。強敵である社会人日本一の松下電工との試合前に、緊張し、高ぶる気持ちを抑えきれない選手たちに行ったものです。涙する選手もいて、この後、プレー開始直後からビッグプレーを連発していったそうです。
ペップトークを見ていただいたところで、本書をご紹介していきます。
どんな悩みを持つ方におススメか?
部下との信頼関係の作り方に悩んでいる、落ち込んでいる友達を勇気づけてあげたい、本番前に緊張してしまう自分を奮い立たせたいなど、他人や自分を励まして、背中を押してあげたいと思っている方におススメです。
この本を読んで得られること
- 人との人間関係を良くする方法
- 人の“やる気スイッチ”を押す方法
- ペップトークの作り方
読もうと思った理由・期待したこと
私が初めて管理職になり、部下を持った時に買った本です。
それまで『人を動かす』、『人を育成』するという観点を持って仕事をしてきた事が無かった私は、部下に対して、自分の働き方の基準で部下に接してしまいました。「部下も当然こう思っているだろう」、「部下もきっとこう行動するだろう」と思っていたのです。
ところが、仕事に対する価値観は人それぞれであることを知り、私が思っていたような行動を部下は取らなかったのです。
当時私が初めて持った部下は、会社の中をたらいまわしにされていた社員でした。ある部下は、しょっちゅう休みを取ってしまうタイプで、有休も残っておらず、欠勤扱いになってしまうほど勤怠が悪かったり、違う部下は、基本仕事に対してやる気0で、自分の思い通りにならないと直ぐに機嫌が悪くなり、いつも誰かの悪口を言い、自分の立場を守ろうとする部下でした。
配属された部門では、常に厄介者扱いされ、たらい回しになっていたのです。
仕事の価値観が違い過ぎる部下に対して、私自身も部下の意識の問題ばかり追求して、仕事がうまく回らないのは部下のせいだと思い込んでいました。
そんなある日、悩んでいる私を見て、あるクライアントの社長さんが、「他人を責める前に、自分を見つめなおしなさい」と、この本をすすめてくださいました。
正直に言いますと、当時社長さんがおすすめしてくれたとはいえ、会社をたらいまわしになってきた私の部下には通用しないだろうと思っていましたが、この本をきっかけにして、部下と向き合えるようになり、勤怠の悪かった部下は、休みを計画的に取るようになりましたし、いつも不機嫌だった部下は、文句ばかり言ってやらなかった仕事も、きちんとやってくれるようになりました。
私は、会社での体験に本著を活かしましたが、人と人との関係構築の部分では、家族や友人などとの関係にも活用できる著書だと思います。
本の概要・あらすじ
- 相手のやる気に火をつけるペップトークの5ルールと4ステップ
- 人のやる気のメカニズムはどうなっているのか?
- やる気スイッチはどこにあるのか?
- 具体的にどうやってペップトークを作って行けば良いのか?
「人のやる気」に焦点が当てられており、具体的な理論や方法を学んだ上で、あなたも1分で相手をやる気にさせることができる”ペップトーカー”になるための方法が紹介されています。
●目次(一部抜粋)
第1章 人のやる気はどこから生まれるのか?
■思いがあれば、人はどんな逆境からでもはい上がれる
■人のやる気が湧き起こるメカニズム
1.「存在ステージ」で相手の存在の重要性に気づく
2.「行動ステージ」で相手が頑張っていることに気付く
3.「結果ステージ」で相手の影響力に気づく
(…以降省略)
第2章 人はなぜ本来持っている実力を発揮できないのか?
■どんな人でも緊張・不安など心理的な壁がある
■本来持っている力(=リソース)を発揮するための心の状態
■相手の実力を引き出すことができなかったリーダー
(…以降省略)
第3章 相手のやる気を最大限に引き出すペップトークのつくりかた
■ペップトークの5つのルール
1.ポジティブな言葉を使う
2.短い言葉を使う
3.わかりやすい言葉を使う
4.相手が一番言ってほしい言葉を使う
5.相手の心に火をつける本気の関わり
■人の心を震わせる最高のペップトーク
■ペップトークはシンプルな4つのステップでつくる
(…以降省略)
第4章 相手のやる気を最大限に引き出すペップトークの伝えかた
■ペップトークの土台は相手との信頼関係
■信頼関係構築にもペップトークの4ステップを使う
■ペップトークと心の状態のメカニズム
(…以降省略)
第5章 あなたのペップトークを実践する
■あなたがやる気を引き出したい相手の感情と状況を常に考える
ペップトークをつくるための質問
あなたの言葉でペップトークをつくってみよう
■ペップトークは人の人生を変える力を持っている
著者のプロフィール
浦上大輔(うらかみ だいすけ)
一般社団法人日本ペップトーク普及協会専務理事
ペップトークの第一人者岩﨑由純氏と一般社団法人日本ペップトーク普及教会を設立
◆浦上大輔公式ホームページ:http://urakamidaisuke.com/
◆一般社団法人日本ペップトーク普及協会:https://www.peptalk.jp/
本著のポイント
ポイント1:やる気が起きるメカニズム
『人は、どういった時にやる気が起きるでしょうか。』
この質問には様々な回答があると思います。
本著の中では、自分には価値があると感じた時に、人はやる気が起きるとされています。自分の価値には2種類あり、「承認欲求」と「貢献欲求」が満たされた時とされています。
私がマネジメントに悩んでいた時、まず初めにこのポイントに取組みました。部下の立場に立った時、どうのような気持ちでいるのかを考えていくと、たらい回しにされてきたことで、私のもとに来た部下は、「どうせまたどこかに飛ばされるのだろう」と、心の中で思っているのではないかと考えました。
そこで私は、その部下が居れくれることが助かっていることを、時間を掛けてコツコツと伝えていきました。そうすることで、部下の中に、この部署にいる存在意義を見つけてくれ、どんどん変わっていきました。
ポイント2:良い行動にフォーカスする
人は、ある行動について指摘されると、意識がそこに向け、その指摘された行動が増える特徴を持っています。そのため悪い行動ばかりを指摘されると、負のスパイラルに入っていってしまうそうです。
このポイントも私は取り組んでみました。もう一人の、常にイライラしている部下に対してです。それまでは、「イライラしてどうしたの?」「〇〇さんに対して、そんなにキツイ言い方はやめよう」などと、直してほしい行動について指摘をしていました。
ポイントを知ってからは、「今日は楽しそうだね。」や「〇〇さんをフォローしてくれてありがとうね」などと、増やして欲しい行動について伝えていくと、イライラしている態度は減っていきました。
このポイントについては、一ヶ月も経たないぐらいで改善効果が見え始めました。
ポイント3:励ましは「行動」を伝える
いきなりですが、甲子園の決勝戦、9回裏、2アウト満塁、5-4の1点差で負けている時に、あなたに打席が回ってきたとします。
バッターボックスに向かう前に、監督から呼ばれ、あなたはこう言われました。
「ホームランを打ってこい!」
きっとあなたはホームランを打たなきゃ、打たなきゃと、めちゃくちゃ緊張してしまい、もしかしたら、身体が固くなってしまうかもしれません。
そうなんです、この「ホームランを打ってこい!」というのは、行動にフォーカスしておらず、行動した結果を指示しているのです。なのであなたは、結果を出さなくてはいけないと緊張してしまうのです。
では、次のように監督から言われたどうでしょうか。
「今日まで頑張ってきた自分を信じて、コースを狙って思いきり振ってこい!」
よし、やってやるぞ!とパワーがみなぎってきませんか?
これは監督がして欲しい行動を伝えているため、伝えられたあなたも、自分がどのように行動すれば良いかイメージが出来、パワーがみなぎってくるのです。
このポイントでは、いままで結果の指示ばかりしていた自分を見つめなおし、その結果に繋がるための行動を指示するようにすると、部下はすんなりと動いてくれるようになりました。
むしろ、その行動について、「こうした方が良くない?」と、自ら考えてくれるようにもなり、効果が大きかったです。
まとめ
今回は、あなたが心を動かした誰かに使うペップトークについて、著書『たった1分で相手をやる気にさせる話術PEP TALK 』をご紹介しました。
実際にペップトークを使ってみると、人は言葉に大きく心が動くことを、感じると思います。
私はまだまだペップトークを使うペップトーカーとは言えませんが、本著に書かれていることを実際に実践し、人の心が変わる場面を見てきたので、本著の効果については体験済みです。
勿論、本著の方法が100%誰にでも効果があるかというと、それは難しい話だとは思いますが、もしあなたが人を動かすことに悩まれていたら、是非試してみてください。
それでは今回はここまでにさせていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
本を一日一冊読めるようになりたい方はこちらの記事もどうぞ↓↓↓