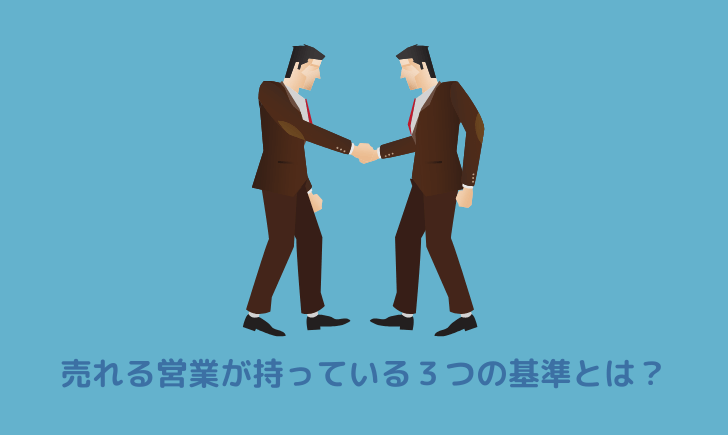・契約後にお客様からの問合せが多くて営業時間が削られる
・新規契約の活動に集中したい
売れる営業って何を考えながら商談しているんだろうと思ったことはありませんか?
実は、この記事で紹介する『売れる営業が持っている契約しない商談基準』を実践すれば、契約後にお客様と揉めることが少なくなって営業活動に集中できるようになります。
なぜなら、私も実際に実践して、精神的負担と営業稼働負担が減り、売上が120%(月平均2件の契約増)増えたからです。
この記事では、売れる営業が持っている契約しない商談基準を3つ紹介します。
記事を読み終えると、今日から契約後にお客様と揉めることが少なくなって売れる営業の営業効率に近づくことができます。
それでは内容に入っていきましょう!
《営業の心得》売れる営業が持っている契約しない商談基準とは?
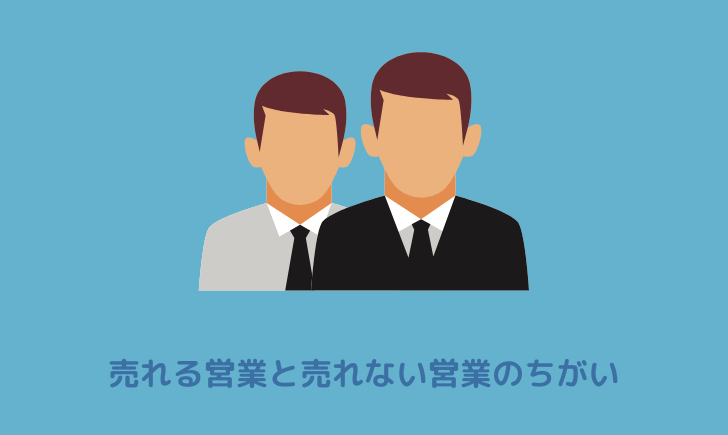
結論からお話します。
売れる営業が持っている契約しない商談基準はこちらです。(↓)
②関係者の役割・スキルが明確になっていない
③スケジュールが守られない
もちろん基準はこれだけではありません。
しかし、この3つの条件を満たした商談は私の経験上、契約後に間違いなくお客様と揉めます。
1つが満たされていないだけでも揉める可能性が高いです。
詳細については後述しますが、なぜ契約するしないの商談基準を持っておく必要があるのか、売れる営業と売れない営業のちがいでお話します。
売れる営業と売れない営業のちがい
・売れる営業 = 契約する商談を選びます。
・売れない営業 = 商談を選ばず何でも契約します。
売れる営業と売れない営業のちがいは色々ありますが、契約するしないの商談基準は必ず持つことをおすすめします。
なぜなら、時間の使い方が圧倒的に変わるからです。
私たち営業が一日に使える時間は、全営業が共通で持っているものですよね。
サラリーマンであれば、9:00~18:00が基本的な活動時間です。
この平等に与えられている時間の使い方が、あなたが持っている商談によって左右されていることに気づく必要があるのです。
売れない営業の失敗
売れない営業時代を過ごしていた私は、とにかく契約が欲しかったです。
上司に罵倒され、買ってくれないと分かっているお客様のところへ何度も通い、しまいにはお客様からも「しつこい!二度と来るな!」と罵倒される毎日。
早くこの状況から脱するために必死でした。
あるとき上司が、売れる営業が商談していたお客様をわたしに引き継いでくれたのです。
ほぼ契約になりそうなお客様だったので、わたしはかなり嬉しくて上司と売れる営業に感謝しました。
売れる営業から引き継ぐとき、「細かくコミュニケーションを取る必要がある商談だけど大丈夫か?」と言われましたが、私は「全然OKです!頑張ります!」と深くは考えていませんでした。
早く契約が欲しかった私は、売れる営業からの忠告など忘れて契約を急ぎました。
無事に契約になったのですが、そのあとが本当に大変でした。
この商談は、先程紹介した『売れる営業が持っている契約しない商談基準』にすべて当てはまってしまう契約だったのです。
案の定わたしは、お客様と大揉めしてしまいました。
お陰でわたしは、しばらく(2~3ヶ月)このお客様の対応に時間を割かれ、新規営業がほとんどできませんでした。
この記事を読んでくれている人には、私のような失敗をしないでもらいたいので、これから紹介する『売れる営業が持っている契約しない商談基準』を覚えて欲しいです。
それでは3つの条件を紹介していきます。
①コミュニケーションワードの定義が異なる

コミュニケーションワードの定義が異なるとは、営業とお客様が商談の中であたりまえに使っている言葉の意味がちがっているということです。
たとえば営業活動の中でも多く見られます。
たとえばお客様のことを、
「見込み客」
「リード客」
「潜在客」
「顕在客」
「リスト客」
「過去客」
「パイプライン客」
「A,B,C客」
など、お客様の契約検討状況によってワード表現が変わります。
またもっと厄介なのが、会社によって使うワードの基準が異なることです。
資料請求をしてくれただけのお客様のことを「リード客」という会社もあれば、「リスト客」という会社もいます。
このワード定義が異なるとどういった困ることが起こるかお話していきたいと思います。
たとえばお客様からリード客に対してキャンペーンを行いたいと要望をもらったとします。
お客様が言うリード客は『資料請求をしてくれただけのお客様』で、営業マンが言うリード客は『商談中のお客様』だった場合、キャンペーン施策を実施する対象者が異なりますので、大きな違いが出てしまいます。
実は私たちは、日常会話の中でもこういったコミュニケーションミスが多く発生しています。
でも、いちいち「その言葉の定義はなに?」なんて確認してたら面倒くさいので、そのままやり過ごしています。
あとで違っていてもごめん!の一言で済んでしまうことが多いので。
しかしビジネスの中ではそうはいきません。
お客様が言うことをきちんと理解してコミュニケーションを取っていくことが重要です。
そうしないと、会話が小さくズレていき、最終的に大きなズレとなって揉めてしまうからです。
前提として、お客様とはコミュニケーションワードの定義が異なることを理解して、定義を共通化していくことに取り組んでみてください。
②関係者の役割・スキルが明確になっていない

『役割』と『スキル』は別軸なので分けて紹介していきます。
役割が明確になっていないとは、
『誰が、いつ、何をするのか?』が明確になっていない
スキルが明確になっていないとは、
『誰が、何を、どうやってできるのか?』が明確になっていない
ということです。
これを関係者内で明確にすることは非常に重要です。
以前わたしは、お客様から「年間のデジタル広告施策を検討してほしい。」と依頼を受けたことがありました。
しかしわたしは、関係者役割とスキルを明確にしないことで失敗したことがあります。
その失敗経験をご紹介していきます。
役割が明確になっていない
わたしはgoogleやSNSを使ったWEB広告の提案を行ったのですが、お客様側が望んでいたのはデジタルを中心としたマーケティング全体計画の提案を行ってほしいということだったのです。
私:デジタル広告施策
客:デジタル広告を中心としたマーケティング全体計画
この二つの内容では、役割も範囲もまったく異なりますよね。
いま振り返れば、こうならない為にはお客様がわたしに望んでいる役割と範囲を明確にしていれば良かっただけなのです。
スキルが明確になっていない
もう一つの失敗は、要員のアサイン(選任)ミスです。
お客様が望んでいたマーケティング全体計画を行うために私が選んだパートナーはWEB広告が得意なパートナーで、マーケティング全体を把握している担当者ではなかったのです。
そのため、関係者間でのコミュニケーションワードも合わないし、マーケティングの考え方も合いませんでした。
予定していた関係者の役割範囲を変えるしかなく、わたしの役割範囲が増えて稼働が大きく増えてしまいました。
実はこの担当者とは知り合ってから時間は経っていましたが、契約後に一緒に組んだことがなくスキルを明確に把握できていなかったのです。
こうならない為には、関係者間で具体的にどのように進めていくか会話を行い、得意なこと・不得意なことを明確にしていく必要があります。
この2つの問題は、関係者内でコミュニケーションを重ねることで解決されることが多いので、契約前に明確にしていきましょう。
③スケジュールが守られない
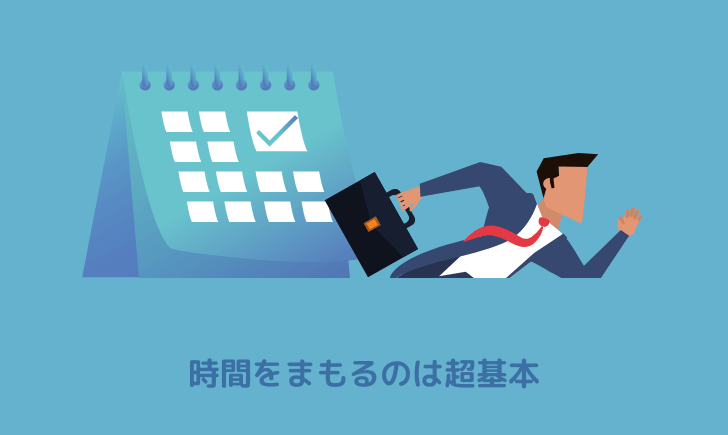
これは紹介している3つの中で最も大切な問題かもしれません。
関係者で合意しているスケジュールが守られないという問題です。
商談でスケジュールを合意する有効性を知らない人はこちらの記事をご参考ください。(↓)

営業から提示するスケジュールは、契約前のスケジュールと契約後のスケジュールです。
『いつまでに、誰が、何をしなくてはいけないか』を提示します。
この提示するスケジュールは、システムを稼働させる日・広告を配信する日など、最終目的日から逆算して作ることが多いです。
最終目的日を遅延することは絶対にできないので、トラブルが起こるリスクも想定して、少し余裕を持たせたスケジュールを作ります。
揉める商談の場合、関係者の中で、忙しさを理由に余裕を持たせているスケジュールを無視して、最終目的日が遅延にならないギリギリのスケジュールで進行する人がいます。
つまり、「最終目的日にさえ間に合えば大丈夫!」と自分勝手に考えて動く人です。
こういう人がいる契約では、タスクがすべてギリギリで動いていくので、何かしらトラブルが起きます。
トラブルが起こったときは既にスケジュールに余裕がないので対応することができなかったり、プラスの予算がかかって対応が必要になったりと揉める可能性が高くなります。
もし商談している中で、スケジュールをちゃんと守れない関係者がいる場合は、その関係者を変えるか、その商談は契約しない方が良いです。
高い確率でトラブルが起こり、揉めることになります。
いますぐ何をすれば良いのか?
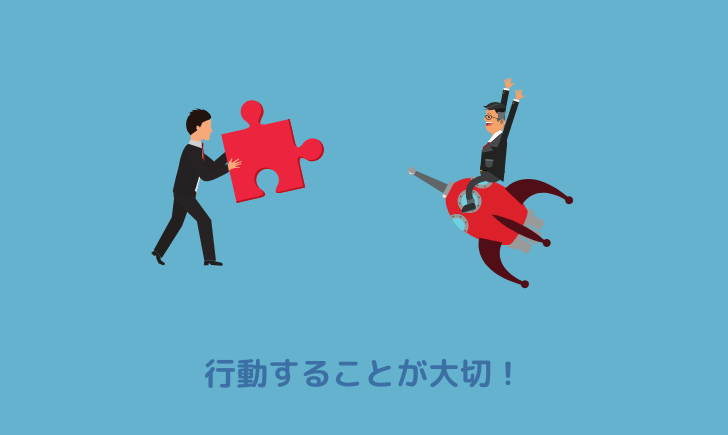
これまで担当した商談の中で契約後に揉めたものがあれば、3つの商談基準を当てはめて振り返ってみてください。
あてはまる部分が多いのではないでしょうか。
営業である以上、「この契約さえ取れば今月のノルマはクリアだ!」と思ったら、目の前にある契約に飛びつきたくなる気持ちはとても分かります。
そんなときは是非もう一度この記事を読み直してみてください。
今月のノルマをクリアするために来月以降苦労するのか、それとも我慢して他の優良商談の発掘に時間を使うのかよく考えてみてください。
わたしがこれまで見てきた売れる営業は、間違いなく後者を選択しています。
まとめ
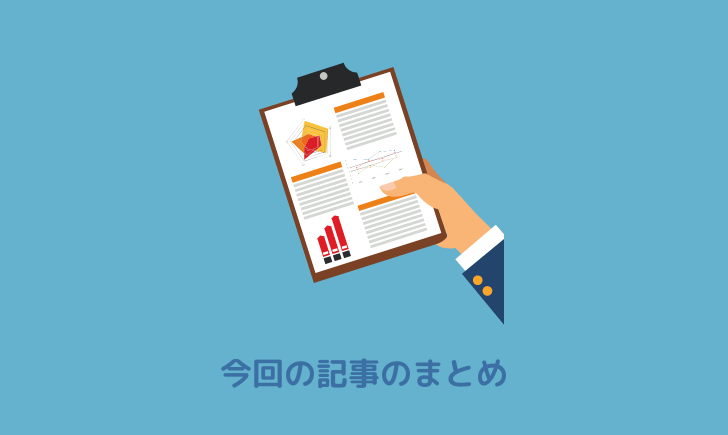
今回は、『売れる営業が持っている契約しない商談基準』について紹介してきました。
この商談基準を実践していくことで、契約後にお客様と揉めることが少なくなって営業活動に集中できるようになります。
ぜひお役立てください。
最後に今回の記事をまとめて終わりにします。
売れる営業が持っている契約しない商談基準
①コミュニケーションワードの定義が異なる
②関係者の役割・スキルが明確になっていない
③スケジュールが守られない
※3つの条件を満たした商談は契約後にお客様と揉める可能性が高い
①コミュニケーションワードの定義が異なる
関係者間ではコミュニケーションワードの定義が異なることを理解する
ワード定義を共通化していくことに取り組んでいく
②関係者の役割・スキルが明確になっていない
役割:『誰が、いつ、何をするのか?』を明確にする
スキル:『誰が、何を、どうやってできるのか?』を明確にする
③スケジュールが守られない
揉める商談ではギリギリのスケジュールで進行する人がいる
こういう人がいる契約はタスクがギリギリで動いていくのでトラブルが起きる
売れる営業と売れない営業のちがい
・売れる営業 = 契約する商談を選ぶ
・売れない営業 = 商談を選ばず何でも契約する
いますぐ何をすれば良いのか?
過去の商談の中で揉めた契約があれば3つの商談基準を当てはめて振り返る
ノルマをクリアするために来月以降苦労するか?
我慢して優良商談の発掘に時間を使うのか?
よく考える
それでは今回はここまでとさせていただきます。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。